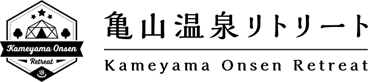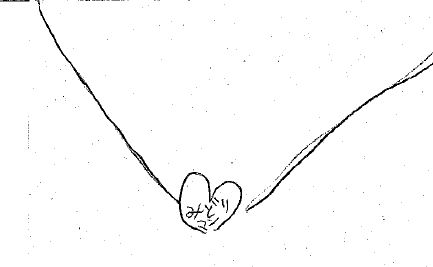冬のプチリトリート

昨晩は、いつものランニング&ヨガサークルのメンバーで横浜みなとみらいを走ってきました!!
今日は、いつもと指向を変えて、日常の中に落とし込める「プチリトリート」のお話をします。
【リトリートとプチリトリートの違い】
①リトリート=日本語で転地療法とも訳される、湯治や養生など自分を整える旅のスタイル。
②プチリトリート=私が提唱している、日常生活の中に落とし込める小さなリトリート(参考記事)
リトリートの達人と呼ばれているからには、さぞかし海外の有名リゾートホテルのリトリートを参加しまくっているんじゃないかと思われがちですが、その逆で小さなリトリートを繰り返して、リトリートの神髄を「日常に落とし込んでこそ」リトリートの達人だと思っています。
さて、晩秋から冬の話に戻します。
この時期は、急激な日照量の低下と気温の低下により、人はバイオリズムを乱しやすいです。
特に冬場は「セロトニン不足」になりがちです。
※セロトニン=精神の安定に関わる神経伝達物質で「幸せホルモン」とも呼ばれ、心の安定を不足すると不安や焦りなどの原因になり、晩秋から冬にかけての「気分の滅入り」の原因になりやすい。

もちろん、私とて皆様と同じ人体の構造で出来た「ヒト」ですから、同じ状況になります。
何となく物悲しい気持ちになったり、ちょっとした一言でいつもより傷ついてしまったり「なんでこんなに焦ってるんだろう?」と思う日が増えるのも、この季節ならではの現象です。

なので、達人としては「自然に任せる」のではなく「自然に合わせる」ことが肝心だとお伝えします。
雨が降れば傘をさすように、暑ければ日陰で休むように、寒い冬にはセロトニンを増やす。
私は、こうしてランニングに参加したり、日々セロトニンを増やす工夫して過ごしています。